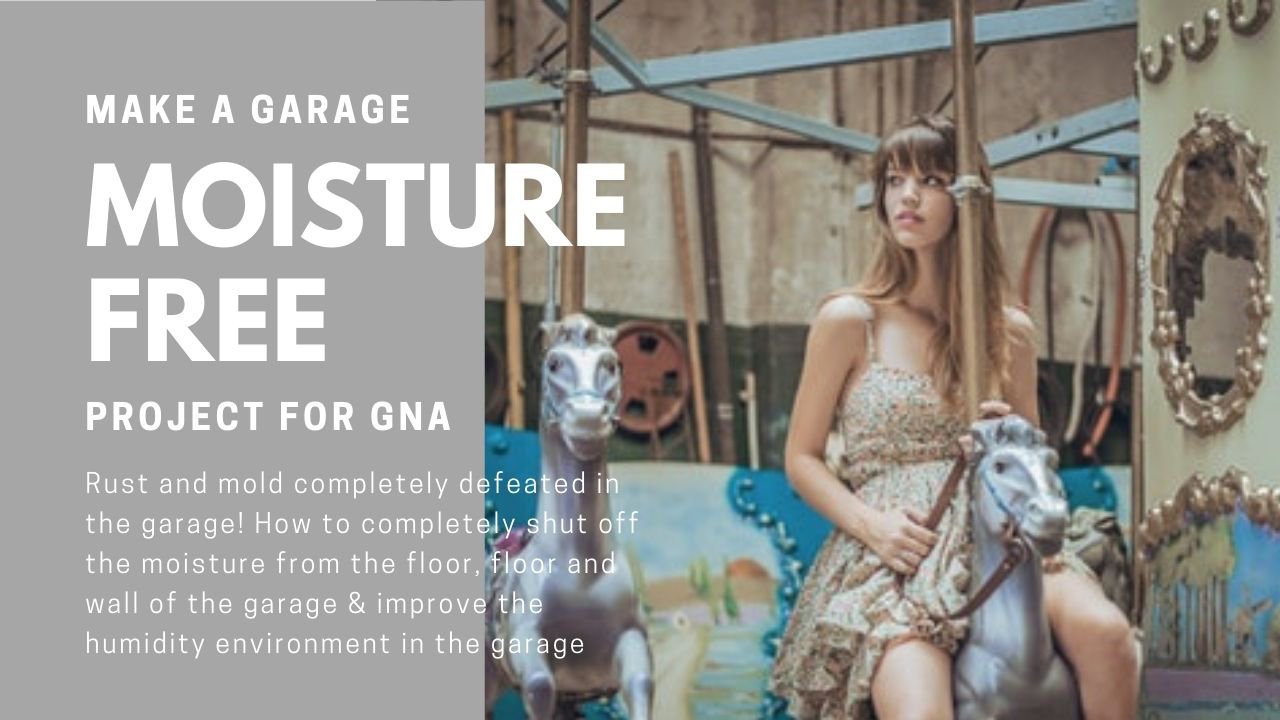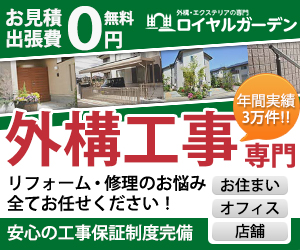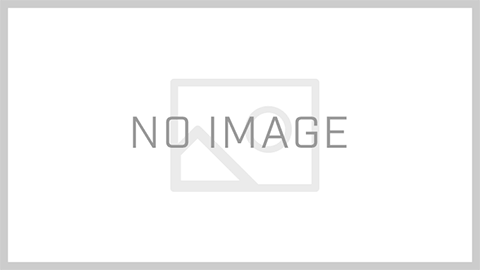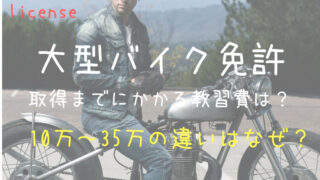車・バイクの金属やレザーにとって、湿気は天敵です。

高温多湿の日本では、壁と屋根で覆っただけの箱だと湿気が溜まりやすいので、特に注意が必要です。
とはいえ、ガレージの湿気対策で 押さえておきたことは2つだけです。
- 室内の空気の循環させる。
- 床や壁に防水処理を施す。
最終手段は、除湿器・エアコンという力技に頼るしかありませんが、まずはガレージ本体への加工や処理で、湿気に強い箱へと改善を図っていきたいですね。

そんなガレージの湿気対策について情報をまとめたので、よろしければご覧ください。
空調対策 湿気の原因と改善方法

原因
ガレージに発生するサビ・カビの原因は、結露です。
【結露とは】

温まった空気・水分を多く含んだ空気が、金属やガラスなどの冷たい物質に触れ、急激に冷やされることで出来る水のこと。
ちなみに、湿気が水に変わる条件は気温によって変わります。
【気温における飽和水蒸気量】
| 気温(℃) | 飽和水蒸気量(g/㎥) |
| 30 | 30.3 |
| 25 | 23.0 |
| 20 | 17.2 |
| 15 | 12.8 |
| 10 | 9.37 |
| 5 | 6.79 |
| 0 | 4.85 |
押さえておきたい空気の特徴は、温かい空気ほど水分量が多く、冷たい空気ほど水分量が少ないという点です。
【気温差が大きい季節や金属・ガラスの表面に結露が起きやすい理由】

ポイントは、金属やガラスは表面温度が低く、空気を急激に冷やす特性があることです。
- 例えば、5℃と15℃では、空気に蓄えられる水分量が倍近く違います。
- 15℃の空気が一気に5℃まで急激に冷やされると、飽和水蒸気量が一気に限界を超え、個体=水に変わります。
結露対策のひとつの解は、「急激に空気を冷やさないこと」と言えますが、完璧に温度管理をしようとすると、設備投資と維持に膨大なコストがかかりますし、効率も良くないです。
そこで、まず最初に対策&検討したいのが、高湿気スポットを、ガレージ内に作らない事です。

対策

空気中の湿気が多いだけでは、必ずしも結露は発生しません。
結露は、気温に応じた飽和水蒸気量を超えなければ発生しません。
また、空気の 飽和水蒸気量や温度 には、ばらつきがあり、常に動いています。
窓や金属面、壁際に結露が発生するからといって、部屋中がびしょびしょになることは滅多にありませんよね。
それは、湿気が溜まりやすいエリアと溜まりにくいエリアがあるからです。
そこで、有効な対策となるのが、空気を物理的に動かすことなんです。
空気を動かす方法は主に3つです。
【空気を動かす 3つの方法と施策の優先順位】
❶通気口を設ける。
単純に壁に穴をあけるだけの施策ですが、効果は絶大!
効果的に通気させるなら、最低でも高所&低所の2ヵ所へ通気口を設けるのがおすすめです。

\マンションの壁でよく見るガラリも効果絶大!/
➋送風機を設ける。
結露し易いポイント=湿気の溜まりやすいポイントは、構造的に決まっています。
溜まりやすいところへピンポイントに風を送ることで、湿気は簡単に散らせます。
また、水分を含んだ空気を攪拌することで、空間内の飽和水蒸気量を均一化する効果もあります。
◎ピンポイント送風に最適!
空気が動けばよいので高い出力は不要です。
CPUクーラー程度でも充分ですよ。
◎ざっくりとした室内攪拌に最適!
強力なサーキューレーターで、一気に攪拌するのがおすすめです。
◎送風機との併用利用はマスト!な 「ON・OFFスイッチ」
ON・OFFスイッチは、自動で送風管理してくれる便利グッズです。
ちなみにこの製品、時間は定期的にズレますし、1年程度でコンスタントに壊れますが、安いですし、機器の寿命をのばしてくれるので、定期的にリピしています。消耗品と割り切って使う分にはおすすめです。
❸室温を上げる。
エアコンや床暖房で空気を温め、空気を対流させます。
気密性の高いビルトインガレージでなければ、効率悪いのでおすすめしません。
取り組む時は、上記の優先で一つずつ実施してみるのがおすすめです。
通気口の数や位置のベストについてまとめました。詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
https://garage-gna.com/vent-460.html
床 湿気の原因と改善方法
原因
床からの湿気が激しい時は、床面の防水処理が不十分なためです。
地面は永続的に水分を含みますので、常に水分を揮発 するのが正常な動きです。

ちなみに、床面がコンクリートになっている場合も安心はできません。
なぜなら、防水処理をされていないただのコンクリートは、吸水⇔揮発を繰り返すため、湿気の温床になる場合があるからです。
原則、ガレージの床材(施工方法)には、素材に関係なく防水処理は必須と思っておきましょう。
対策

床からの湿気対策は2つです。
【床からの湿気対策】
❶床材に防水処理を施す。
わたしが最もおすすめするのは、既存ガレージにも簡単に施工できる、ビニール&石膏ボードのミルフィーユ加工です。
わたしのガレージはこの加工を行っていますが、効果抜群です。

コンクリート床の場合、防水塗料を塗るのも効果的で、DIY可能な塗料も市販されています。
ただし、コンクリート塗料の質・耐久性を考えると、業者に依頼したほうがコスパはよいと思いますね。
➋床下換気を作る。
水分を含んだ湿気は重いので、地面に近い位置に溜まりやすいです。
可能であれば、住居と同じように床下換気を設けるのが理想です。
【日本家屋の特徴】
古代日本では、穀物の保存庫は、湿気を避けるために地面から高い位置に作られました。
また、日本家屋は、床下に通風孔を設けることで、効果的に湿気を逃がす作りになっています。
高床×床下換気は理想ですが、コスト的に厳しい事も多いです。
少なくとも、既存のガレージを床付きタイプへ改造するのは、現実的ではありません。
ちなみに、バイク用のプレハブガレージだと、「床付き」というタイプが床下に空間ができるため、湿気にも有利です。
\わたしのガレージはイナバの床付きタイプです/
敷くだけ簡単!防湿床の施工方法や注意点などをまとめました。詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
https://garage-gna.com/floor-moisture-526.html
壁 湿気の原因と改善方法

原因
通常、結露が起きやすいのは、床面に近い壁や金属パーツ周辺です。
壁の上方や遮蔽物のない箇所に結露や浸みが出来ている場合、雨漏りの可能性が高いですね。

対策
壁の対策も、最終的には床同様に、防水処理を施せばよいのですが、根本的な解決も必要です。
【防水加工前にやる事】

- 発生源の特定
- 雨漏りの被害状況の確認
- 雨漏り箇所の補修
ガレージのタイプにも依りますが、発生源の特定と補修の程度を見極めるのは素人には難しいので、業者にお願いするのが無難です。
まとめ

ガレージ内の愛車にサビ・カビを発生させないためには、結露を生まない空気の循環と、水を吸収しない(防水処理済みの)壁・床を設置することが重要です。
これから建てる人は、万全の湿気対策を盛り込んで制作してください。
既にお持ちのガレージに対策したい方は、以下の優先で対策をしていくとよいと思います。
【ガレージ内の湿気対策と対策の優先】

- 通気口を設ける。
- 床下に防水加工を施す。
- サーキュレーターを設置する。
なお、壁の上方や遮蔽物がない箇所に発生するカビや浸みにお悩みなら、それは雨漏りが原因かもしれません。
根本的な補修や、その他リペアも必要なケースがありますので、業者に対策を依頼しましょう。
サビやカビに強くなる、ガレージ環境の改善方法については以上となります。
バイクガレージに多いプレハブタイプなら、本記事に掲載した内容を参考にすれば、大部分が解消できると思いますよ。

対して、原因が根深く、根本的な防水対策をしないと改善されないのが、フルコンクリートやビルトインタイプのガレージでしょう。
また、ビルトインタイプは、なまじ室内という意識もあるため、エアコンで温度を上げたり、除湿器に頼りがちですが、居住スペースからの温かい空気の流入を遮断するのが最良の手段だったりします。
対策の一手段として、ご留意くださいませ。

それでは、引き続き素敵なガレージライフをお楽しみください。